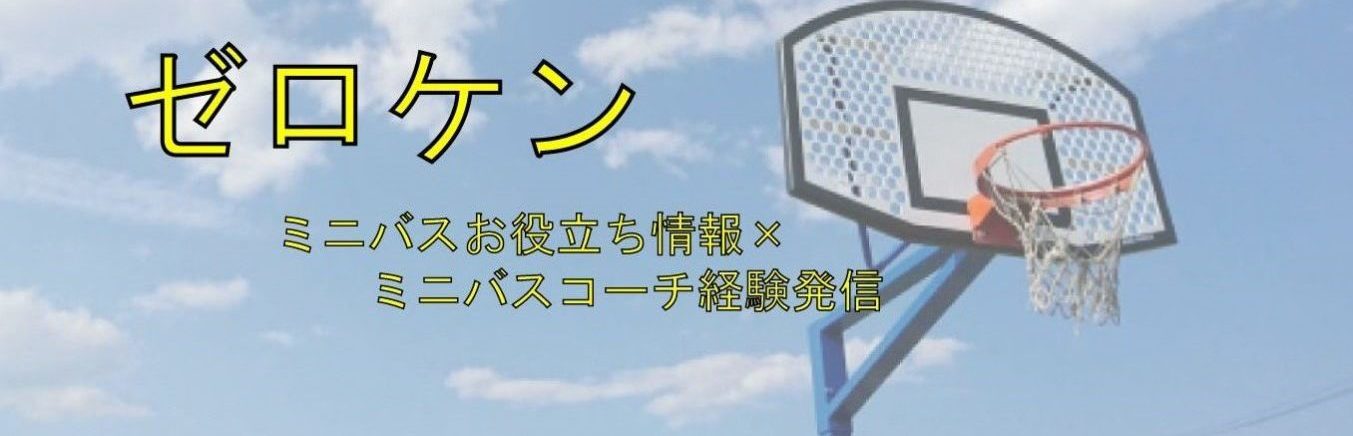ゼロケンです。
今回はミニバスにありがちな初歩的ミスについてお伝えしていきたいと思います。こちらを改善できれば実際のゲームがスムーズに進められますので是非参考にしてください。
バイオレーションやファール(バスケ)
一番あるのはドリブルをつこうとした際のトラベリングかと思います。
この突き出しは低学年の頃は必ずと言っていいほど起きてきますね。
ボールを突き出す前に助走をつけようとするために軸足をあげてしまい12とステップを踏みながらドリブルをついてしまうためトラベリングになってしまいます。
ただ低学年の始めたばかりの子達に細かなルールを説明しても理解できませんので私はトラベリング、ダブルドリブルは気にせずプレイしよう。
むしろリングに向かっていかないほうがダメだよ。一番ダメなのがぽつんと立って何もプレーをしない。
またボールの後ろを追いかけるだけ、ボールマンを後ろから追いかけるだけもダメだよと伝えています。
プレーに参加しないというのが一番成長できない部分ですのでとにかくボールを持ったらごオールに向かいシュートを狙うように伝えています。
年少の頃は大会もないですしモチベーションとしたら毎日楽しいということですので、楽しむことを重視した方がよいですね。
高学年になりゲームや大会に出るようになるとしっかりモチベーション、動機付けができますからその時点で突き出しを直していこうで大丈夫かと思います。
具体的な修正方法をお伝えしたいと思います。
ルール上はボールをキャッチしてから一番初めに床についた足を離した状態でドリブルをしてはいけない。
ですのでこちらを頭において指導していくことが大事です。
かといってピボットやステップを使わず両足をペタッとついた状態でドリブルをつき始めても(これもよくあります)一対一の場面で相手を抜き去るということはできにくくなりますので、入りの段階でピボットの概念を教えることが大事です。
軸足に重心を置きつま先側(親指側の付け根付近)を中心に回転運動をしながら体全体を回すことができる。
1:ピボットの概念
またミートからストップの仕方も教えていきたいですね。スライドストップと両足をつくジャンプストップ。
2:ストップの概念
この後に突き出しに入るのがスムーズですが、人間の歩く動作を子供は本能で覚えています。
12と足をついてしまうと次は3。つまり軸足をあげたくなってしまうのは本能的に仕方がないと思います。私が実践していることはドリブルは1、2の”2”の足と同時に着く。という風に教えることでトラベリングを回避していけます。
3:2の足で突き出す
実際そう教えることで初歩の段階でのゲームでトラベリングになることはまずなくなりました。
低学年の場合まだ抜けきれないでトラベリングになるパターンも多々ありますが失敗してしまうときは”ピボットでボールを返せばいい”と伝えます。
そして練習を積み重ねていけば改善されていきます。他の突き出しの技術は次の段階で取り組んでいけば良いです。
まずはトラベリングにならないというのを一番に教えたいですね。
よくあるファール
その次によくあるのが一対一で抜かれ際に手を引っ掛けてしまいファールを取られてしまうケースです。
気持ちは分かるのですがイリーガルな手という風になります。
その前に全く足が動かず簡単に抜きさられてしまい、さらにダッシュもせず自分のペースでボールを追いかけて戻るという光景もありますが、ここは更に前段階として最低限クリアしたいところです。
逆にファールになっても足を動かして止めろという風に教える方が後々ディフェンス力は伸びてきます。
退場恐れずに相手にぶつかってでも向かっていく姿勢を教えていけばいいですね。
話を戻しますが、子供達は触れ合いが起こってしまうと全てがファールだという認識でいます。
ぶつからないで止める方法として本能的に手を使ってしまうんでしょう。
ですので指導の仕方としては、胴体を使って止めるものだという風な感覚を持たせていくことが大事です。
実際のゲームの場面でもゴールラインを取っている状態で接触があってもファールにはなりません。
さらに無理やりぶつかり合いが起こればオフェンスファールになります。
また上のレベルになればなるほどこのぶつかり合いが起こってきます。
初歩の段階から県大会レベルまで進もうとなればぶつかって止める。
正確には受け止めて止める。というディフェンスが必死になってきますので、しっかりと教えていきたいところです。
接触の際に両手を上げてと指導される方もおられると思いますが、私の場合は前に出していた方のトレースハンドを使ってギリギリまでプレッシャーをかけさせます。
接触しそうなところでその腕を体にくっつける。
片方の手は上げておきシュートチェックやパスカットに備える。と教えています。
受け止めた後やそのままポストプレーなど仕掛けられた時にアームバーとしてまた腕を出していくこともできますし最初から両手を上げていくよりは相手へのプレッシャーにもなります。
是非参考にされてください。
ゴールラインは全カテゴリ共通
ゴールライン、インラインをしっかり押さえておく。ミニバスだけでなく高校や社会人になっても必要な理論ですのでミニバスの頃から徹底していくことは大事です。
また抜かれるにしても直線的にゴールラインを抜かれるのではなく一歩でも粘って遠回りさせることでカバーリングやチームディフェンスがしやすくなるということも教えておけば良いです。
一対一をゲーム全ての場面で完璧に抑えるということはほぼありませんから、抜かれたら負けなんだではなく抜かれても次の段階のディフェンスをするんだ。
最終的にリバンドを取るまでがディフェンスなんだ。という概念を植え付けておくことは大事です。
抜かれたのは良くないけどその後チームで守るのがバスケットなんだと教えていきたいですね。
ボール出しでよくあるミス
シュートを入られた後やサイドラインからのスローインの時に、ボールをインターセプトされてしまいそのままイージーシュートを決められる場面も良くあります。
ボール出しの準備もしておかなければいけないですね。こちらは全員とならなくともボール運びをする選手に絞ってもよいです。
駄目なパターンはその場に立って”はいはい”や”よこせ”というだけで、ボールが出た瞬間ディフェンスに入られてそのままインターセプト。
1:レシーバーが動かない
改善のポイントとしてはオフボールでのカットプレイでディフェンスを左右に振り切るイメージです。
キャッチの前のミート、キャッチ後のピボットまでは準備しておきたいところです。
振り切る動作ですがポイントとしては左右で振り切るのであればレシーバーはミドルラインを越えるぐらいに左右に大きく。
これによってディフェンスの角度やフットワークやボディコントロール視野の確保などの技術が必要になり、高度な技術が必要で振り切りやすくなります。
振り切ろうと思っても相手のフットワークが鋭くて。うまくインターセプトされてしまう。パターンもあります。
その際はしっかり下半身と胴体で相手をブロックして押さえてボールをもらう。ということになります。
2:相手をロックして
ボールが出る瞬間に相手を少し押し込むぐらいでいいと思います。ブロックをしてもその場で貰おうとすると後ろから手が出てきますのでもらう瞬間はしっかりミートする。
次の段階でブロックされた相手は無理やり前を取ろうとしてきますから今度はゴール側でなく反対側に出していく。
ロブパスのような形を教えていくことになります。
3:裏へロブパス
この際は表側にフェイント入れてから、一気に裏側にボールを入れていく。さらにパスを出す人とのアイコンタクトやターゲットハンドのコミュニケーションも必要になってきます。より高度になってきますね。
ここら辺まででインターセプトはなくなるかと思いますが、それでもうまくを出せないという時はボールマン1人とレシーバを2人にしたスクリーンプレーなどが必要になってくると思います。
まとめ
私もよく素人の先生に指導してもらった時はとにかくボールは12でもらってというふうに教えられました。
しかしルール上は色々なもらい方があり単純なスライドストップだけではゲームに勝つレベルにはなれません。
コーチは”なぜできないんだ”ではなくできないのが当たり前だからしっかり教えていこうと逆に燃え上がるくらいにしていきたいですね。
覚悟があれば大丈夫です。私にだって出来たのですから。今回はここまでです。