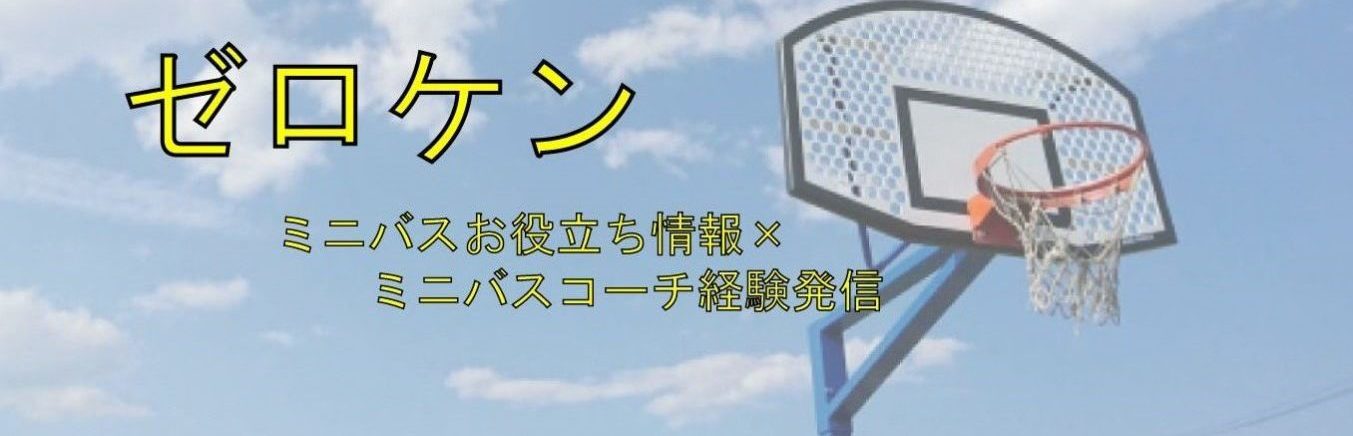ゼロケンです。
今回は新人戦の時期もありて学年によくみられるプレーについてお伝えしていきたいと思います。良いものも良くないものもありますので是非ご一読ください。
低学年はそもそもできなくて当たり前(バスケ)
バスケットのカテゴリ分けでは大きくU12とU10に分かれています。
U12は当然のごとく6年生以下。U10は4年生以下になります。
低学年の子達はそもそもミニバスケット、バスケットに慣れていないわけですからミスが起こるのは当然でゲームをしてもミスだらけのガチャガチャしたものになります。
この子達に経験を積ませてしっかりとしたバスケットの形に持っていくのがコーチの役割です。
極端に言うとこの状況で選手に対して怒ったり怒鳴ったりしているコーチがいたならば考え方を変えないといけないですね。しっかりやらせられないのは全てコーチの責任なのですから。
但ししつけの部分。挨拶やきびきびとした態度などは多少厳しくても教えていかないといけないと思います。
そもそもしつけは親の指導の範囲ですけどね。
どちらに攻めてどちらを守るのか
まずはじめにどちらのゴールに攻めてどちらのゴールを守るのか。このことがわからない子が多いですね。
センタージャンプの時から右往左往。。。バスケットのディフェンスでは自分のマークマンと守るべきゴールの間。ゴールライン(インライン)にポジションを取るのが基本ですがそれができない。あるあるです。
また後半になると攻めと守りがコートチェンジで変わりますからポジションも逆になります。これも理解できない。あるあるです。
対策としては経験を積み重ねるのが一番なのですが、日々の練習時のゲームでしっかりと意識させることで実際のゲームのさいにはまずどちらを守りどちらを攻めるのか自ら考えるようになりますから。
選手に初めの段階でしっかりと自分で考える癖をつけさせていけばよいですね。あとは一緒に出る上級生がいるならば必ず低学年に声がけをさせるようにさせればよいですね。
ジョギング感覚に動いてしまう
もう一つはコート全体を走り回らなければいけないのに自分のペースでジョギングのようにコートを移動するケース。これもあるあるです。
コーチが伝えた時は頑張って走るが、自分で判断したときはジョギング並み。
これもバスケットはどういったものか。スポーツとはどういったものか理解できていないだけですね。
スポーツは相手と競い合う。相手のスピードより上回って相手より先に攻めるゴールに近づき守るゴールに戻る。
といった認識が足りないだけですので試合の時だけでなく日頃の練習時から教えていきたいですね。
また移動する距離も最短距離を移動した方が当然相手より有利に立てるわけですから。走って行くコースを教えていくのも大事ですね。
状況判断ができない。
もう一つはオフェンスの際ディフェンスが自分のの前にいようがいまいが自分のやりたいことをプレイしようとしてミスになってしまう。
まだまだ相手に対応したプレーを選択するということができませんから仕方のないことです。
相手が目の前にいてもボールを前に出してドリブルをしようとして簡単に相手に取られてしまう。
ディフェンスが目の前に立ちふさがっているのにリングしか見えないでのんびりセットシュート。
簡単にブロックされてしまう。あるあるです。
後々色んなプレーを身につけてくればしっかり前を向いて状況判断しプレーの選択が出来るのですが、それには経験を積まないとできない部分です。
対策としては判断するような場面を練習でどんどん作ってあげる。コーチは焦ることなく経験を積ませていくのが大事ですね。
練習の中でも単に遊び感覚のゲームを繰り返すのではなく現段階での低学年の目標をしっかりと設定して目的をもって練習そして練習の中のゲームをさせていくことは大事です。
伸びそうな子の判断材料
私が低学年を見ていてバスケットがうまくなりそうだなと判断する材料ですが、肉食系か草食系かといった見方をしています。
良い悪いは決してないのですが言われなくてもボールを肉食動物のエサを取りに行くように追いかけるような選手は後々うまくなっていますね。
これは教えてできない本能といった要素ですね。草食系でボールを見ているだけで追いかけない。ディフェンスも常に相手の後を追いかけるといった選手はうまくなるまでの時間がかかります。
これもコーチがしっかりと指導をしていけば解決できるものです。
まとめ
他にもいろいろあるあるですが一貫していえることはコーチは成功する体験もそうですが、失敗をする体験もどんどんさせるべきですね。
成功した時は当然本人も嬉しいですし周りも褒めてくれるでしょう。
失敗した時にただ単に何で出来ないんだって怒って終わらせるのではなく原因はこうだったからうまくいかなかった。
こうすればうまくいくという解決策を示してあげる。
次へのモチベーションを維持させる。その経験が積み重なれば、高学年には自分で判断できるようになってきます。そうなるためにある程度の期間が必要ですから。
コーチは忍耐をもって取り組んでいきたいところです。やがてそれが花を開き子供達の素晴らしいプレーが見れる喜び。
その未来に対して夢を持ちコーチは日々取り組んでいきたいですね。
覚悟があれば大丈夫です。私にだって出来たのですから。今回はここまでです。