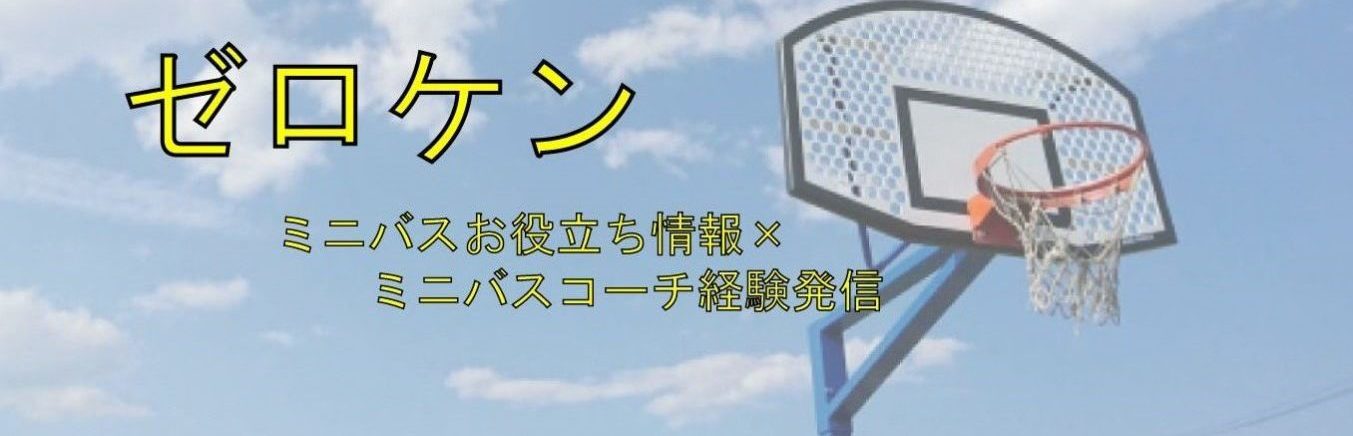バスケはぶつかれば単純にファールとはならない。実はボディコンタクトのあるスポーツ。
正しい認識がなければただコンタクトをしてもファールになってしまう。
正しい認識がなければコンタクトすることで逆に足が止まってしまう。
ケースによってコンタクトの仕方を切り替えてディフェンスができるようになりたい記事。

ゼロケンです。
今回はミニバス、バスケにおけるボディコンタクトの部分についてお伝えさせていただきます。
こちらをご覧いただくことで
1:バスケットはボディコンタクトのあるスポーツでありぶつかり合いがあってもファールにならないケースがある
2:正しい認識がなければただコンタクトしてもファールになってしまう
3:正しい認識がなければコンタクトすることで逆に足が止まってしまう
4:ケースによってコンタクトの仕方を切り替えてディフェンスができるようになる
ですので是非最後までご覧ください。
ミニバス上位チームと地区一回戦レベルの一番の違い
私は街にミニバスが無い地区でチームを立ち上げ、全くの初心者たちへミニバスを指導するところからスタートさせました。
下記カテゴリで記事一覧⇊
ゼロから県大会の様子
念願の県大会出場も叶えたのですが、私が感じている全くゼロの状態から立ち上げた頃と今現在の大きな違いを考えると
「ボディコンタクトのあるなしを前提においてバスケをしているか」
が一つあります。

正しいポジションでのボディコンタクトはファールにならない
バスケは表向きは接触をするとファールになるルールがあるのですが、もう少し噛み砕いて説明すると正しいポジションでのボディコンタクトはファールにならないというほうが正しいです。
こちらを理解しないために初心者や低学年のゲーム、地区の一回戦レベルではディフェンスで接触が起こりません。
そのためオフェンスは楽々ゴールへとオフェンスすることができて勝ち上がるチームは大差をつけてしまうことがあります。
またオフェンスをしたくても予想もしないボディコンタクトが起こるわけですから当然ボールキープが出来ない。うまくボールを運んできてもまた予想外のコンタクトに普段の練習のようなオフェンスが出来ない。
走り負けも当然ありますが一番はボディコンタクトの差だと感じています。
逆のケースで自滅
またこのコンタクトも正確に理解していないと
「激しくディフェンス=ただぶつかる。ただボールをとりにいく」
となってしまいぶつかった段階でファールとなります。
間違った身体のぶつかり合い。
間違った手の接触でファール。
結果
フリースローなどを与えてしまう。
ファールアウトしてしまう。
ファールにならなくても
無理やりボールを追いかけてブラインド側(ウラ)にパスを展開されてしまう。なども起こりますね。
コンタクトをしっかり認識
ミニバスにおいても小学生なりのボディコンタクトをしっかり理解させることでファールにならずに相手にぶつかり合いのプレッシャーをかけ続けることができます。
強固なディフェンスのチームへと生まれ変わることができ結果的に勝ち上がっていけるチームになってきますのでしっかり身に付けていくことが大事ですね。

ボディアップとスティック
今回はボディアップとスティックの二つを私なりの考えを交えながら説明させていただきます。
足を動かせとボディコンタクトは反比例!!
こちらは私が長年ミニバスの指導に関わって感じている事なのですがコンタクトは
足を動かそうとすればするほどコンタクトには弱くなり、受け止めようとすればするほど足が動かなくなる。足を動かすとコンタクトは反比例!!
します。
おいおいっ!!
そしたらディフェンスはどうやって守ればいいのよ!?
ということになりますが大丈夫です。こちらを説明しますので(*’ω’*)
結論からすると
ケースによって使い分けるというのが正しいです。
一般的なディフェンススタンスといえばこちらですが。。。


コチラの違い分かりますか?「マンバのような視線!!」「膝の位置」
も気になるのですが今回のテーマであるボディコンタクトの面から説明させていただきますと
骨盤の上に上半身が乗れば乗るほど骨盤と股関節は体を支えようとする方に機能し足が動かないのです。
ただし体を支えているわけですからコンタクトには強くなる。つまり反比例の関係になります。
足を動かしたいときは上記のコービーの画像のように骨盤の上に上半身を置かないようにする。が正しいスタンスになります!
ミニバスでの光景
低学年の練習でよく見られるのですがスライドステップの練習をしても上体を前に倒すことができないため骨盤の上に上半身が完全に乗ってしまう。
当然ながら足が動かない状態でスライドの練習をしてしまうため、動かない足を補うために大腿部分(太もも)を動かしながらスライドしてしまうという間違った動きになってしまいます。
というかそうしないと動かないので子供たちはそうする。素直ですから。。。
骨盤と股関節と上半身の傾きを正しく教えることが重要です
ボディアップ
アウトサイドにおいてディフェンスのスタンスは、お尻を後ろに持ってきて上体を前に倒す。
こうすることで骨盤と股関節が上半身を支える必要が少なくなり、股関節を動かしやすくなる。肩甲骨も同様なのですが股関節と肩甲骨は特殊な骨の形状をしておりぐりぐりと回すことができる骨の形状をしています。
大腿骨を回すように使えればディフェンスの動きが多様なものにすることができ、相手のオフェンスに対応する事が出来ます。
ただし動かしやすくする分「反比例」ですから上体を支えにくいということになります。ですからコンタクトそのものには弱いものになります。
イメージとしては
ボディアップで相手のドライブを止めていく。
⇊
それでも負けずに縦に仕掛けてくる相手には今度は身体を起こしていき、足を多少動きづらくしてでもコンタクトに対して踏ん張りをきかせられる体勢に持ってくる。
という切り替えが必要になってきます。


相撲で見てみましょう
ボディコンタクトの代表として相撲を例にとってさらにご説明します。
相撲における四股の形はまさにディフェンスのスタンスです。上体を前に倒して股関節を動かしやすくする。
実際の取り組みでは立会いでぶつかり合った瞬間上体を起こしに行きます。
「まず足を動かなくする攻防ですね!」
土俵際まで追い込むと相手は最後の踏ん張りを見せますが
骨盤に上体を乗せることで踏ん張れる体勢を作っています。
「押し合いに強い体制をとっているですね!」


バスケも同じです
バスケでも24秒のオフェンス中で
序盤のディフェンスでは
「足を動かすことを優先したボディコンタクトを意識する」
こちらのボディアップで防げれば成功!
それでも処理しきれない次の段階の強い縦へのコンタクトは
「押し合いに負けないことを意識した体制スタンスでボディコンタクトしていく」
足を動かすよりこれ以上インサイドに近づけないことが最優先!!
ですね!
別の場面ですがインサイドの攻防では
「初めから押し合いに負けないことを意識した体制スタンスでボディコンタクトしていく」
事も必要になってきます。
すべて同じ認識で処理しようとすれば不利な状況が生まれやすくなり結果的に相手に得点を許してしまうことになりますね。
チーム全体で認識する強さ
一対一の場面で最終的に足が動かずにオフェンスに抜かれてしまったとしても大丈夫です。バスケは5:5のチームディフェンスです。
「この1秒、0.5秒の時間稼ぎ」
が非常に重要でチームとしてヘルプディフェンスをしやすくし
最終的なオフェンスの目的である
「シュートを決める」
事が困難になってきます。
バスケは一対一で抜くことは試合の一場面でしかなく、「シュートを決めさせない!」が本当のディフェンスの目的になります。
例え一対一が抜かれたとしても
ボディコンタクトを頑張った
⇊
時間稼ぎできた
⇊
ヘルプが間に合った
⇊
チームとして得点を許さなかった
でチームとしてディフェンスは成功になります。
強いチームはこのコンタクトの認識がチーム全体でできています。
チーム全体でコンタクトを使い分け
抜かれた場面でも前段階で「踏んばって時間稼ぎをしている」
ヘルプの準備が整う「最終的に相手チームがチームとして得点できない」
⇊
勝利の可能性が高い!!
となりますね。一試合通じて偶然守れたは無いですね!
スティック
最後にインサイドのボディコンタクトの技術である「スティック」についてもご説明します。
インサイドのディフェンスでは
ボールを持ったオフェンスの前に少しでもスペースがあれば即シュートに持っていかれます。
「相手を振り向かせないためにスティック」
「相手に少しのスペースも与えないスティック」
が必要になります。
骨盤に思いっきり上体をのせて押し合いの準備始めからマックスです。
膝はまげてディフェンススタンスで腕は両腕上にあげます。



ボディアップとスティックについてまとめ
いかがだったでしょうか?
皆様も是非ボディアップとスティックを認識し使い分けてコンタクトに強い激しいディフェンスをできるプレイヤーになってください。
バスケはこの他にもたくさんの理論がありますから本当に奥が深いです。
関わている間日々アップデートです。
ゼロケンの過去のバスケ理論練習についての記事はこちら⇊
カテゴリ:練習と理論
存在皆無のゼロの状態から県大会を叶えた記事はこちら⇊
カテゴリ:ゼロから県大会
覚悟があれば大丈夫です。私にだって出来たのですから。今回はここまでです。