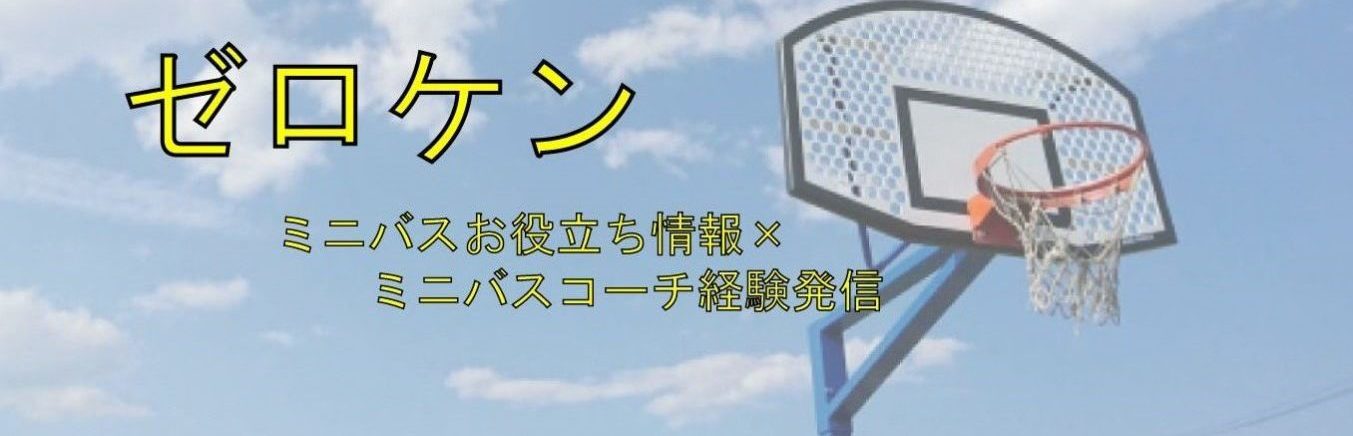ゼロケンです
今回は勉強や生活にも活用できるのですが
記憶に残すために感情を利用するといったテクニックと構造をお伝えしたいと思います。
ミニバスにとっても活用できますので是非ご参考にされてください。
感情を出すことで記憶力アップ
前回は感情をコントロールするために使うルーティンの重要性をお伝えさせていただきました。
【ミニバス】習慣化するためにルーティーンを身につける
今回は逆に記憶に残すために感情を利用します。
感情出したら失敗するんでないの!?言ってなかったっけ!?
私が日々お伝えしているのは感情をコントロールするのが重要という事ですのでお間違え無いようにしてくださいね。
人の行動の原動力は感情ですので前回の記事を参考にされてくださいね。
昔から記憶に残る事には必ず感情が伴っている
皆さんは小さい時のことや昔のことでよく覚えてることはありますか?
私が未だに鮮明に覚えているのは中学校の時に通っていた塾の先生に教わったあることです。
これは”一年のカレンダーの中で31日がない日を覚えるコツ”
という事で教わった事なのですが
当時の講師の先生は学生のアルバイト講師だったと思いますが。。。
「西向くサムライ小の月」と教えてくれました。
解説すると
2,4,6,9、サムライは武士の「士」が漢字の11に見えるからといったもので
この5つの月が31日がないのです。
後になると色々覚え方もあるようですが
当時中学生の私には今でいう「スッキリ―!!」といった爽快感と
物覚えた感動で今でも忘れずに覚えています。

負の記憶であっても感情によって鮮明になる
また修学旅行や遠足の楽しい思い出などは皆さんもいまだに思い起こすことがあると思います。
負の記憶もそうですね。
あの時嫌な思いをしたとか苦しい思いをしたな~などフラッシュバックのように思い出すことがあるかもしれません 。
これは楽しい記憶は楽しかったという感情が伴っており記憶がより強固なものになっているというメカニズムになります。
負の記憶も原理は同じで 負の感情が伴って記憶が強固なものになっているのです 。
逆に感情が伴わないでやっつけ仕事したことや単純作業なんかは全く記憶に残っていないと思います。
私が読んだメンタルを学びパフォーマンスアップにつなげた参考書籍
私が参考にしている書籍もたくさんあるのですがお勧めのメンタルコーチングの本です。
このメンタルコーチは飯山晄朗さんというかたである出来事がきっかけで一気に有名になったかたなのです。
それが高校野球の石川県大会決勝で起きた球史に残る「大逆転劇」です。
簡単に言うと八回が終わって0対8で負けていたところから逆転して勝利し甲子園に出場した!のです!
これが偶然に起きたものではなく感情を伴ったメンタルをコントロールすることで起こせたのだということです。詳しくは読んでみてくださいね。
記憶のメカニズムは脳の構造からも立証済
飯山さんが別の講義で言っていたのですがこの記憶のメカニズムやパフォーマンスのメカニズム。
これは実際に脳の中の構造的にも正しいものだというのです。

脳内の構造
大脳辺縁系
が脳の真ん中にある状態
その前側に
前頭葉
大脳辺縁系とつながって脳幹
大脳辺縁系が感情本能の部分で記憶の部分の前頭葉が感情の部分とつながっている。
大脳辺縁系から各筋肉への命令を通す脳幹とつながっている。
つまり脳の構造上感情が記憶やスポーツパフォーマンスを左右している構造になるという事です。
ミニバスや小学生に活用し学習効率を上げてパフォーマンスアップも実現
このことをミニバスにおいても利用するべきですね。
喜怒哀楽をうまくコントロールさせられるようにトレーニングに取り入れることで学習効果を高めることができる。また試合中も有利に運ぶことができるという事です。
時にはルーティーンを使って感情を抑えていく。
逆にチームで盛り上がっていこうというときは感情を爆発させていく。
我慢するべきところで我慢を続けチャンスを待つ。
感情の存在をミニバスの現場に認知させよりレベルの高い練習環境を作る
子供達への具体的なアプローチとして練習中、試合中に感情を伴ったプレーをさせていけばよいという事ですね。
喜びだけでなく喜怒哀楽です。
出来た喜びや達成感をセットで教えることがインプットには非常に効果があるという事です。
スポーツは楽しいことばかりではないがそれすら克服
また苦しみや怒りの感情も人間ですから当然のことでそのものの存在自体を否定しても人間として不自然。
大事なことは自分の心をコントロールできるようになる。
それがゲームに対してプラスなのかマイナスなのかをきちんと理解させることで選手が使い分けられるようにする。ゲームで一番勝ちたいのは選手なのですから自分でしっかり選択出来るようになります。
パフォーマンスアップの解説
脳の構造からパフォーマンスの向上も感情が関係しているという事ですが
大脳辺縁系と脳幹が隣り合わせのため
良いメンタルの状態では神経伝達もはやいのだそうです。
昔ながらの教え方は正しかったのか
日本の学生スポーツの歴史というのは長らく部活動、修行、勉強、であり
感情を抑えて指導者に従っていくというのが美学のようになっていました。
それが負の側面であっても閉鎖的なため表に出ることが少なかったのですが
今やメディアが発達しネットやSNS で沢山の情報が手に取れるような時代になりました。
昔ながらの教え方が悪かったということは一概には言えません。
私だってそうやって育ってきた中年男子ですし十分鍛えられた部分はあります。
まとめ
今回は記憶のメカニズムの解説からミニバスにおいても感情をコントロールすることの重要性をお伝えしました。
はじめにお知らせしたルーティーンにより感情をコントロールする方法も一緒にご覧くださいね。
【ミニバス】習慣化するためにルーティーンを身につける
小学生ってメンタルで試合が変わる部分って多いですよね。
技術だけでなくメンタルの面からもレベルアップした環境を作っていきたいですね。
覚悟があれば大丈夫です。私にだって出来たのですから。今回はここまでです。